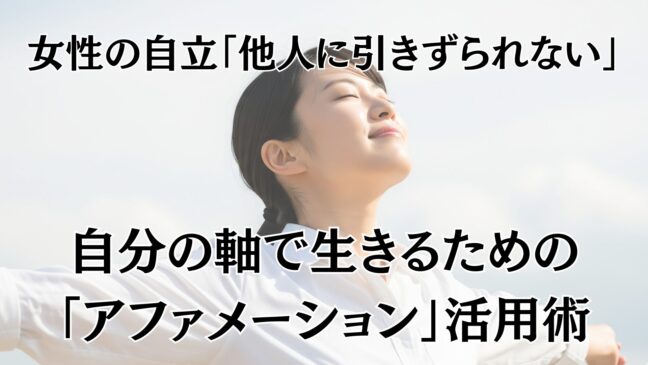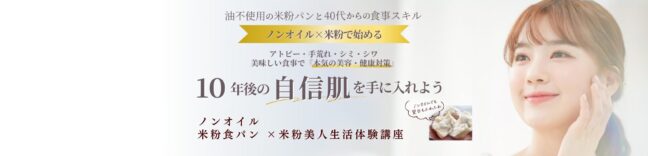【血糖値の悩み解消】「甘いものやめられない」を卒業!疲れた時の賢い糖質活用法
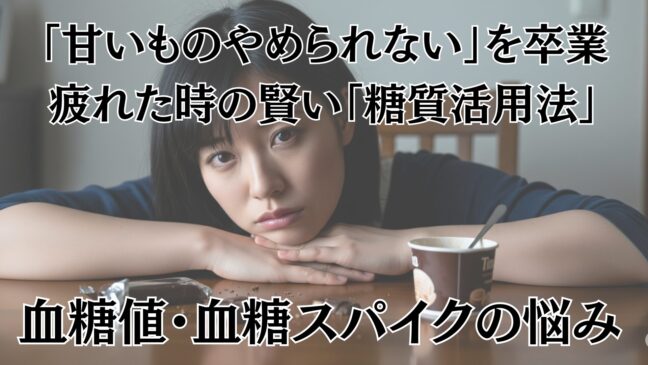

甘いものは良くないなーと思いつつ、どうしてもやらなくてはいけないことがあったり、身体や精神的に辛いと、甘いものに頼りがちです。やめたいのですが、甘いものを食べると、元気になっって、動けるんです。だから、習慣になってしまっているというか…血糖値の数値も高いし、どうしたら、いいのか困っています。
と、お悩みですね。
毎日家事や育児、お仕事に頑張る中で、「あ〜、疲れた!」「もう頭が回らない!」と感じる瞬間、ありませんか?
そんな時、ついつい手が伸びてしまうのが、チョコレートやクッキー、ジュースなどの甘いもの。 「疲れた時には甘いものが必要だから!」そう思って、当たり前のように食べている方も多いかもしれません。
でも、その甘いものを食べた後、かえって「ドーンと疲れる」「眠くなる」「集中力が続かない」と感じる経験はありませんか?
実は、血糖値との上手な付き合い方を知ることで、その悪循環から抜け出し、お菓子に頼らずに疲れを癒し、集中力を維持することができるんです。今日は、あなたの「甘いものとの関係」を見直す、新しい視点をお伝えします。
本記事はこんな方におすすめです!
✔️血糖値の数値(ヘモグロビンA1c・HbA1c)が高いのに甘いものがやめられない方
✔️甘いものを食べないと、元気が出ない、特に午後が辛い方
✔️血糖値を急上昇させない上手な糖質の摂り方や活用方法が知りたい方

みやなりちあき
私、みやなりちあきは、教室未経験の人の教室開業のゼロを1にして、10年続く教室の土台作りをサポートする、教室開業コンサルタントで、米粉・グルテンフリー・アレルギー対応料理研究家、米粉レシピ開発・商品開発のサポート事業をしています。米粉講師の育成をしている、ヘルシーライフデザイン協会代表理事を務めています。
教室開業11年、米粉研究歴11年、子どもが0歳の時に料理教室を立ち上げ、レッスンを継続、協会を設立、述べ1400名の受講生を指導、講師育成をしてきました。企業や行政のサポートまで行っています。
教室ビジネスと米粉の教育のプロフェッショナルとして活動しています。
グルテンフリー生活を中心とした食事法で、血糖値の安定を意識した食生活を10年続けています。食事管理で、摂食障害、鬱を克服しました。
講義実績 (敬称略)
東京都 Start Up Hub Tokyo TAMA カルチュアコンビニエンスクラブ株式会社(蔦屋書店)米コ塾米粉カンファレンス 株式会社ぐるなび など
米粉事業・レシピ開発相談実績
実績例(敬称略)
貝印 農林水産省 青森県中泊町農政課 CookPadTV 日和ファーム 有限会社エール
合同会社well being プラスナチュリ 彩華 など
目次
甘いものが食べたいほど「頭が回らない」「疲れた」と感じた時、体で何が起きている?

なんで疲れると、甘いものが欲しいって思うのでしょうか?

「疲れたから甘いものが欲しい!」と感じる時、脳や体はSOSサインを出しています。糖質は、脳や体を動かす大切なエネルギー源なので、その感覚自体は間違いではありません。
しかし、どんな糖質を、どんなタイミングで摂るかが、その後のあなたのコンディションを大きく左右します。
脳は唯一のエネルギー源としてブドウ糖(糖質が分解されたもの)を優先的に利用します。 疲労やストレスを感じると、脳のエネルギー消費が増大。さらに、ストレスホルモン(コルチゾールなど)が分泌され、血糖値を上げようとします。
この時、脳は即座にエネルギーを補給しようと、手軽に吸収される甘いものを強く求めます。

そうだ!甘いものを食べると、早くエネルギーになるんだったぞ!おーい、早く甘いもの食べてー!
これは、脳が一時的なパフォーマンス維持のために発する自然な信号です。
しかし、ここで「精製された砂糖(グミ、飴、チョコ、など)」を摂取すると、体内で次のような反応が起こります。
血糖値の急上昇
精製糖は消化吸収が非常に速いため、ブドウ糖が血中に一気に流れ込み、血糖値が急激に跳ね上がります(血糖値スパイク)。
インスリンの大量分泌
急激に上がった血糖値を下げるため、膵臓からインスリンが大量に分泌されます。
血糖値の急降下
大量のインスリン作用により、今度は血糖値が下がりすぎてしまいます。この急激な血糖値の降下こそが、午後の眠気、だるさ、集中力の低下、イライラ、そして再び甘いものを強く求める「二次的な甘いもの欲求」を引き起こします。
アドレナリン・コルチゾールの再分泌
血糖値が急降下すると、体はこれを「緊急事態」とみなし、再びストレスホルモンであるアドレナリンやコルチゾールを分泌して血糖値を上げようとします。これにより、体は常にストレス反応にさらされ、疲労が蓄積しやすくなります。

つまり、「疲れたから甘いもの」という感覚自体は間違いではありませんが、選ぶ糖質の種類とタイミングを間違えると、その後の体と心に大きな負担をかけ、かえって疲労や不調の悪循環を招いてしまうのです。
甘いもの(精製糖)を摂った時に、体と心で起こっていること

血糖値が急に上がったり、インスリンがいっぱい分泌されたり、ストレス対応のホルモンが分泌されることは分かったけど、それが、何故良くないの?なんとなく、血糖値が高いのは、糖尿病とかになるから良くないのは、わかるんだけど…

OKです!何となく、血糖値が高いのは良くないのはわかるということで、口にした甘いものが、お菓子や清涼飲料水などの「精製された糖」を多く含む場合、体の中ではどんなことが起こっていくのか、解説しますね!
血糖値の急上昇と急降下(血糖値スパイク)
精製糖は体内で素早く吸収され、血液中のブドウ糖(血糖値)を急激に上昇させます。すると、体は血糖値を急いで下げるために、大量のインスリンを分泌します。その結果、今度は血糖値が急激に下がりすぎます。「血糖値スパイク」という状態が起こりやすくなります。
心の変化
この急降下の際に、脳はエネルギー不足を感じて、またすぐに甘いものを強く求めます。同時に、イライラしたり、集中力が散漫になったり、気分が不安定になったりすることも。
体の変化
急降下によって、強いだるさ、眠気、疲労感が襲ってきます。まるでジェットコースターに乗っているような状態です。
脳の報酬系の活性化と「依存」
甘いものを口にすると、脳の報酬系(快感を感じる神経回路)が活性化され、ドーパミンなどの「快楽物質」が瞬時に分泌されます。

これにより、単に「幸せ〜」と感じるだけでなく、脳の機能が一時的に高まったかのように、やる気や元気が出たように感じたり、ぼんやりしていた頭がすっきりしたように感じたりすることがあります。
特に、カフェイン(コーヒー、エナジードリンクなど)と砂糖を一緒に摂取すると、両者が異なるメカニズムで脳の報酬系や覚醒作用に働きかけるため、より強い「覚醒感」や「一時的な高揚感」が得られやすいとされます。
ある40代女性のお話です。その方は、お子さんの習い事の送迎を車でしていました。毎日が時間が詰め詰めで、プレッシャーを感じ流生活をしていました。もともと、甘いものが好きでした。
習い事の送迎の際に、ある時、車で待っている時に、カフェオレと菓子パンを食べたそうです。とても癒されたそうで、もう一回、もう一回とやっているうちに、その時間が定着、習慣化してしまい、やめられなくなっていってしまいました。
メロンパンなどの、甘いパンを食べてお子さんを待つのが習慣になってしまったのです。そんな生活を続けた結果、その後、病気になってしまったのです…
脳は、強い快感を繰り返し求め、「もっと欲しい」という渇望を生み出します。
その結果、同じ量の砂糖では満足できなくなり、摂取量が増えてしまう「砂糖依存」のような状態に陥る可能性が指摘されています。
これは、快感がやがて習慣となり、やがては「砂糖や甘いものがなければ、不調を取り除けない」というサイクルにつながります。
慢性的な炎症の促進
精製された糖の過剰摂取は、体内で「AGEs(終末糖化産物)」という有害物質の生成を促したり、腸内環境を乱したりすることで、慢性的な微細な炎症を促進する可能性があります。これが、肌荒れや原因不明のだるさ、さらには様々な生活習慣病のリスクを高めるとも言われています。

「AGEs(終末糖化産物)」は、老化物質。シミやシワ、クスにも原因にもなります。甘いものが、習慣になっていて、頻繁に血糖値スパイクを起こしている人は、「老けやすい」食生活になっているとも言えます。
「疲れた」時に、「甘いもの」お菓子以外でできること

では、「疲れたから甘いもの」というループから抜け出すために、お菓子に頼らずにできることは何でしょうか?まず、「疲れた」と感じた時にできる簡単なことから、やってみましょう。
まずは「水分補給」
脱水は、脳の機能を低下させ、集中力の低下やだるさを引き起こす大きな原因です。まずは、コップ一杯の水をゆっくり飲んでみましょう。意外とこれだけでスッキリすることも。
軽い運動・ストレッチ
席を立ち、数分間軽く歩いたり、肩や首を回したりするだけでもOK。血行が促進され、脳に新鮮な酸素や栄養が供給されて、頭がクリアになります。
深呼吸・瞑想
ストレスや疲労で呼吸が浅くなっていることがあります。数分間、ゆっくりと深呼吸を繰り返したり、簡単な瞑想アプリを使ったりすることで、脳と心をリフレッシュできます。

おすすめは、アンドルー・ワイル博士が提唱する「4-7-8 呼吸法」です。4秒吸って、7秒キープ、8秒かけて、丹田まで深く息を吐き切ります。私も寝た姿勢で、この呼吸法を良くやっていますよ。瞑想として、15分ほど行います。スッキリしますよー。
短時間の仮眠(パワーナップ)
午後に眠気を感じたら、15~20分程度の短い仮眠は、その後のパフォーマンスを劇的に改善します。深く眠りすぎないよう、アラームを設定しましょう。
賢く糖と付き合う!「血糖値スパイク」を防ぐ食事のコツ

日常の食事で、血糖値の急激な上昇を抑え、穏やかなエネルギー供給を続けるためのコツを知れば、疲れにくく、集中力を持続できる体へと変われます。食事のポイントを解説していきますね。
1. 「セカンドミール効果」を味方につける!
「セカンドミール効果」とは、1日の最初にとる食事が、その後に食べる食事の血糖値上昇にも影響を与えるという驚きの効果のこと。
つまり、朝食に食べるものが、昼食後の血糖値にまで良い影響を与えうるのです。逆を言えば、「菓子パンを朝ごはんにすると1日が地獄」ということです。
朝はパン♪…じゃなくて、朝はご飯♪…をおすすめします!
我慢やイライラ、ぼーっとする…手放したいですよね。
ポイント: 糖質を摂る前に、食物繊維やタンパク質を先に摂ること!
具体例:
食事の最初に野菜サラダ、きのこ類、海藻類、具沢山のスープなどを食べる「ベジファースト」。納豆とめかぶ、卵。わかめや野菜の味噌汁でOK。野菜が取り入れにくいのなら、ミニトマトならお手軽ですね。
糖質を摂る際は、一緒に卵、肉、魚、豆腐などのタンパク質をしっかり摂る。
朝食に、玄米ご飯、雑穀ご飯、白米でもいいですが、食物繊維が豊富な野菜や海藻を忘れずに。または全粒粉パンや、米粉パンなら、たっぷりの野菜や卵を添える。
寝かせ玄米は、ずっというて置けて置けるので、1人ぐらしの方にも、玄米は家族が食べないんだよね…という人にもおすすめです。
2. 「食べる順番」を意識する
これはセカンドミール効果とも関連しますが、一食の中での食べる順番も非常に大切です。
野菜・海藻・きのこ類 → タンパク質(肉・魚・卵・豆類)
→ 糖質(ご飯・パン・麺など)
この順番で食べることで、食物繊維が糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急激な上昇を抑えることができます。
3. 「糖質の質」を選ぶ
同じ糖質でも、その種類によって血糖値への影響は異なります。
避けたいのは「精製された糖質」
白い砂糖、白いパン、清涼飲料水など、食物繊維が取り除かれたものは血糖値が急上昇しやすいです。米粉パンも、グルテンフリーですが、単体で食べると、これらと同じです。気をつけましょう。
選びたいのは「複合糖質」や「自然な甘み」
玄米、雑穀米、全粒粉パン、さつまいも、かぼちゃ、果物など。これらは食物繊維が豊富で、血糖値の上昇が緩やかです。
当社の米粉パンは、小麦を使っていないだけでなく、砂糖の量を控えめにしたり、素材の甘みを活かしたり、食物繊維をプラスしたりすることで、血糖値に優しい工夫をしています。
まとめ
あなたらしい「賢い糖質活用」で、心と体を心地よく満たそう
ここまで、あなたが「疲れたから甘いものが欲しい!」と感じる理由や、その裏で体と心に何が起こっているのか、そして、お菓子に頼らずに血糖値を穏やかに保ちながら、賢く糖質と付き合う方法についてお話ししてきました。
「甘いものをやめる」というのは、決して簡単なことではありません。それは単なる食欲だけでなく、疲労やストレス、あるいは脳の快楽物質が絡み合った複雑な問題だからです。
でも、大切なのは、「完璧に甘いものを断つ」ことではありません。
あなたが目指すべきは、「血糖値の急上昇・急降下」に翻弄されず、心と体が本当に心地よいと感じる「糖質との付き合い方」を見つけることです。
頭が回らないと感じた時も、お菓子に頼る前にできることはたくさんあります。
「食べる順番」や「糖質の質」を意識するだけで、血糖値の波は穏やかになります。
そして何より、「自分はこう食べたい」「こうすれば体が喜ぶ」という、あなた自身の感覚を大切にすること。
「甘いものとの関係」は、あなたの心の状態も映し出す鏡のようなものです。自分を責めることなく、少しずつでも、「賢い糖質活用」へとシフトしていくことで、きっと食事がもっと楽しく、そして心身ともに安定した毎日を送れるようになるでしょう。
米粉を取り入れて、血糖値管理・身体・メンタルを整える食生活「米粉美人生活」体験講座は毎月、少人数制で開催しています!
当教室では、油や小麦を使わないパン作りを通して、血糖値が気になる方でも安心して楽しめるパンのレシピだけでなく、「我慢する」ではなく「積極的に選んで楽しむ」食の選択肢を広げるお手伝いをしています。
家族と美味しく楽しく10年後も幸せに食べられる食事を一緒に目指しませんか? ぜひ一度、当教室のレッスンで、新しい食の発見を体験してみてください。
健康のために米粉パンを作ってみたい。
ストレスで食べ過ぎをしてしまうのが気になる。
イライラして甘いものをやめられず、罪悪感を感じている。
健康的な食事を送りたいけど家族とぶつかっている。
家族が米粉のものを食べてくれずに悩んでいる。
ノンオイルの米粉パンをおいしく家族にも提供したい。
偏食の子供が菓子パンばかり食べて、米粉の手作りパンを食べてくれない。
自分がダイエットに縛られて苦しい。
シミやシワ対策ができる美味しい食生活が知りたい。
自分だけでなく、家族間の様々な悩みをお持ちの方が集まる、
米粉の取り入れ方を学び体験講座です。