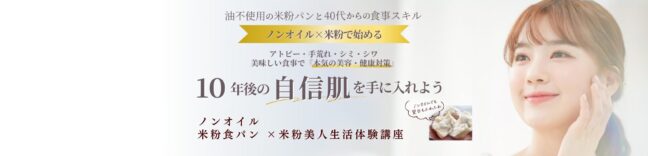【健康食に潜む摂食障害】オルトレキシアとは?制限食・禁止食


うちのこ、「健康的な食事にしてほしい!」「健康に悪いよ!食べたくない!」といって、
決まったもの以外、食べてくれなくなってしまって…
どうしちゃったのかしら…栄養バランスも悪い気がするし、心配だわ…ネットで調べたら「オルトレキシア」っていう摂食障害かもしれないって、気になっているんだけど…
と、お悩みですね。
心配ですよね。まずは、状況を整理して、オルトレキシアがどのようなものかを、一緒に勉強していきましょう。大丈夫だよと、無理に食べさせようとしても、食べてくれません。まずは、「知ること」からはじめてみましょう。
本記事はこんな方におすすめです!
✔️健康的な食事じゃないと食べないと言い張るお子様やご家族がいる
✔️自分自身が、食事にこだわりすぎて、家族と馬が合わず、窮屈に感じている
✔️自分自身やご家族が、オルトレキシア、摂食障害なのではないかと心配している

みやなりちあき
私、みやなりちあきは、教室未経験の人の教室開業のゼロを1にして、10年続く教室の土台作りをサポートする、教室開業コンサルタントで、米粉・グルテンフリー・アレルギー対応料理研究家、米粉レシピ開発・商品開発のサポート事業をしています。米粉講師の育成をしている、ヘルシーライフデザイン協会代表理事を務めています。
教室開業11年、米粉研究歴11年、子どもが0歳の時に料理教室を立ち上げ、レッスンを継続、協会を設立、述べ1400名の受講生を指導、講師育成をしてきました。企業や行政のサポートまで行っています。
教室ビジネスと米粉の教育のプロフェッショナルとして活動しています。
グルテンフリー生活を中心とした食事法で、血糖値の安定を意識した食生活を10年続けています。食事管理で、摂食障害、鬱を克服しました。
講義実績 (敬称略)
東京都 Start Up Hub Tokyo TAMA カルチュアコンビニエンスクラブ株式会社(蔦屋書店)米コ塾米粉カンファレンス 株式会社ぐるなび など
米粉事業・レシピ開発相談実績
実績例(敬称略)
貝印 農林水産省 青森県中泊町農政課 CookPadTV 日和ファーム 有限会社エール
合同会社well being プラスナチュリ 彩華 など
目次
「健康的な食事」いつの間にかあなたを苦しめていませんか?

「健康的」な食事なのに、苦しめるって、どういうこと?健康にいいなら、そっちの方がいいと思うんだけど、違うの?

「健康」は、いいんですが、「身体的」な健康にこだわるあまり、「心の健康」を失ってしまうケースがあるのです。「健康とはこういうものだ」という、信念が強くなりすぎ、「強迫観念」にまで成長し、追い込まれてしまっていると、どんどん、生き辛くなってしまうのです。
「健康にも気をつけなきゃ」「家族のためにも、栄養のあるものを」そう思って、食事に気をつけている方も多いのではないでしょうか。
でも、その「健康的」な食事が、いつの間にかあなたを息苦しくさせていませんか?
「ちゃんとしたものを食べなきゃ」「これは体に悪いからダメ」…
そんな思いが、あなたの心を縛り付けているとしたら、それはもしかしたら「摂食障害」の一種、「オルトレキシア」という状態に近づいているサインかもしれません。

「健康的な食事」は、より良い人生を送るために必要なんですが、それが、あなたの心の自由や、人とのつながり、日々の小さな喜びを奪ってしまうとしたら、それは本当の健康と言えるでしょうか?
今回の記事では、「オルトレキシアとは、何なのか?」詳しく解説していきますね。
オルトレキシアって、なに?

オルトレキシアって何?「摂食障害」って言うけど、何が違うの?

聞き慣れない言葉かもしれませんね。簡単に言うと、「健康的な食事」へのこだわりが、度を超して、かえって心身の健康を損なってしまう状態のことです。
例えば、こんなこと、心当たりはありませんか?
-
「添加物が怖いから、スーパーで買えるものがほとんどない」
-
「グルテンフリーや糖質オフを徹底しすぎて、食べられるものが限られてきた」
-
「お菓子や揚げ物なんて、もってのほか!食べたら罪悪感でいっぱいになる」
-
「家族が普通に食べているものが、自分には『不健康なもの』に見えてしまう」
-
「外食するのが、気が重い。食べられるものがないから」
-
「自分の決めたルールから少しでも外れると、ひどく落ち込んだり、自分を責めたりする」
赤で書いた部分が、重要な箇所です。
行動や思考に、「強い制限」がかかっているのが、わかりますか?
「健康のため」と始めたことが、だんだんと「~しなければならない」という義務感に変わり、少しでもルールを破ると強い罪悪感に襲われる。
まるで、自分の中に厳しい「禁止食リスト」ができてしまい、それ以外の「許可食」だけしか食べられなくなってしまうような状態です。

ここで知って欲しいのが、
「許可食」と「禁止食」
摂食障害では、食べ物に対する独特の捉え方から、特定の食品を厳しく区別する傾向があります。それが「許可食」と「禁止食」です。
許可食(きょかしょく)とは?
「許可食」とは、摂食障害を抱える方が「これなら食べても大丈夫」「太らない」「健康的だ」と自分に”許可”を出して、安心して食べられると思っている食品のことです。
例えば、「生野菜なら安心」「鶏むね肉のササミならセーフ」「水だけならOK」といった具合に、カロリーが低い、脂質が少ない、添加物がないなど、自分なりの厳しい基準で選ばれます。
しかし、この「許可」は決してポジティブな意味合いではありません。むしろ、「これしか食べられない」という制限の裏返しであり、不安や強迫観念からくるものです。
禁止食(きんししょく)とは?
一方、「禁止食」とは、摂食障害を抱える方が「これは食べてはいけない」「食べると太る」「不健康になる」と強く信じ込み、極端に避けてしまう食品のことです。
お菓子、揚げ物、パン、ご飯、乳製品、油を使った料理など、一般的に「美味しい」と感じられるものが対象になりがちです。これらを口にすると、強い罪悪感や自己嫌悪に苛まれるため、必死に我慢しようとします。
許可食と禁止食、その決定的な違いとは?
許可食も禁止食も、どちらも「健康的であるべき」という強すぎる思い込みから生まれる、食べ物への偏った認識です。
-
許可食:「これなら安全」という、限られた安心感を求める対象。
-
禁止食:「これは危険」という、強い恐怖と罪悪感を伴う対象。
健康な状態では、私たちは食べ物を「美味しい」「好き」「栄養がある」といった基準で選びます。しかし、摂食障害の渦中にあると、この「許可食」「禁止食」という区別が、食事の選択を支配し、食べる喜びを奪い、最終的には心身の健康を損なう原因となってしまうのです。
この「許可食」と「禁止食」のリストが長くなればなるほど、食べられるものが減り、栄養が偏り、外食や人との食事が困難になり、あなたはどんどん孤独で苦しい思いをしてしまいます。

「健康」は、本来もっと自由で楽しいもの
私たちは皆、「健康になりたい」と願う気持ちがあります。それは素晴らしいことです。でも、その健康への願いが、あなたをがんじがらめにして、食べる楽しみや人との交流を奪っているとしたら、それは本末転倒ではないでしょうか?
考えてみてください。本当に健康な状態とは、どんな状態でしょう?
-
特定のものを「食べちゃいけない」と追い詰められることなく、心穏やかに食事ができること。
-
たまには好きなものを食べて、「美味しい!」と心から喜べること。
-
家族や友人と、わいわい食卓を囲む時間も楽しめること。
-
完璧じゃなくても、「まあ、いっか!」と自分を許せること。
健康的な食事は大切ですが、それがストレスの元になってしまっては、意味がありません。心と体のバランスが取れていることこそが、本当の「健康」ではないでしょうか。しかしながら、誤字病のある方は、食事を気をつけなければなりませんし、欲に振り回されて、食事が乱れるのも、また違います。
ポイントは、
ご自身の「体」が苦しんでいないか?
ご自身の「心」が苦しんでいないか?
ご自身の「人間関係」が、苦しんでいないか?
これらをチェックしてみてくださいね。
では、どのようにすれば、オルトレキシアにならずいられるのでしょうか?
次の項目で、オルトレキシアに陥る思考の癖について、みていきましょう。
オルトレキシアの原因と入口
オルトレキシアは、「心理バイアス」にかかっていることが多いです。
オルトレキシアの入り口となる「心理バイアス」は、いくつか複合的に作用していると考えられますが、特に顕著なものを挙げると以下のようになります。
確証バイアス (Confirmation Bias)

確証バイアスとは?
「自分の信じたい情報ばかりを集め、それと矛盾する情報を無視したり軽視したりする傾向」
これがオルトレキシアの大きな入り口の一つです。どう作用するか、みていきましょう。
「〇〇は体に悪い」という情報を目にすると、その情報ばかりを強く信じ込み、その情報が偏った見解であったり、科学的根拠が乏しかったりしても、深く検証せずに受け入れてしまいます。
逆に、「〇〇もバランスよく食べることが大切」といった情報は、「自分には当てはまらない」「専門家ではない人の意見だ」などと無視してしまう傾向があります。
SNSなどで「同じような健康志向」を持つ人の意見ばかりをフォローし、自分の考えをさらに強化していきます。
2. 完璧主義 (Perfectionism)

「完璧主義」はよく聞くかもしれませんね。
「何事も完璧でなければならないと考え、少しの欠陥も許容できない心理特性」
オルトレキシアになりやすい人の多くにこの特性が見られます。
「完璧な健康食」を目指し、少しでもルールを破ると許せない、という強迫的な思考につながります。
食材の選び方、調理法、食べるタイミングなど、あらゆる面で「こうあるべき」という理想を高く設定し、それが少しでも崩れると強い自己否定感に陥ります。
自分だけでなく、他人の食事に対しても完璧を求め、批判的になることがあります。
3. コントロール幻想(Illusion of Control)

コントロール幻想は、心配性の人に多いかと思います。
「自分の行動によって、物事を完全にコントロールできると過信してしまう傾向」
これは、不安な気持ちを打ち消すために現れることがあります。
「食事を完璧にコントロールすれば、病気にならない」「老化を防げる」「常に最高の健康状態を維持できる」といった、過度な期待を抱きます。(実際、リスクは下げられても、そんなことはありえないですよね。)
実際にはコントロールできない健康面(遺伝、環境要因など)も、食事のコントロールだけで全て解決できると思い込み、そこに過剰なエネルギーを注ぎます。
不安やストレスを感じやすい人が、食事のコントロールという「分かりやすい形」で安心感を得ようとすることがあります。
4. 認知の歪み(Cognitive Distortions)

「認知の歪み」って聞いたことがありますか?あまりないかもしれませんね。ちょっと難しい響きですが、簡単に言うと、
「気持ちがザワつく思考のクセ」と考えると簡単でしょうか?
「物事を客観的に見られず、偏った見方をしてしまう思考のクセ」のことです。私たちは「誰でも」、多かれ少なかれこの「思考のクセ」を持っています。安心してくださいね。
これは特定のバイアスというより、思考のクセ全般を指しますが、オルトレキシアの入り口となる様々な歪みがあります。
白黒思考(All-or-Nothing Thinking):「完璧な健康食か、不健康な食事か」というように、極端に二分化して考える。「少しでも添加物が入っていたら全部ダメ」など。

ゼロか100か、「100以外は無駄」のような思考になることです。当然、グレーがあってもいいのだけれど、許せないのですね。
食事で言えば、少しでも砂糖が入っていたら、「だめ!」とか、他で言うと、
「今日ジムに行けなかったから、もうダイエットは失敗だ。全部やめてしまおう。」とか、「絵を描いてみたけど、プロのようには描けないから、もうやめよう。」とか、「プレゼンで一つでも言い間違えたら、もう全てが台無しだ。」のような、例が挙げられます。
破局的思考(Catastrophizing):「これを食べたら大変なことになる」「病気になる」など、最悪の事態ばかりを想像し、過剰に恐れる。

破局的思考とは、
どんな小さな問題でも、すぐに「最悪の事態」を想像し、「ありえないような悲劇的な結末ばかりを考えてしまう思考のクセ」です。
まるで、心のスイッチが「最悪のシナリオ」に固定されてしまっているような状態です。
例:人間関係で意見の相違があった時
思考の例: 「友人と少し意見が合わなかった…これで嫌われる。もう二度と口をきいてくれなくなるかもしれない。私にはもう誰もいなくなる…。」
現実的な可能性: 意見の相違は自然なこと、相手もそれほど気にしていないかもしれない、後で話し合えば解決すること、など。
影響: 人との衝突を極端に恐れ、自分の意見を言えなくなったり、人間関係を避けるようになったりします。
実際に、このようなやりとりをしたことがあります。

先生、さっき、腸に悪いものを食べてしまったんです…
私の腸内細菌は、きっとこれで、最悪な状態になってしまった。きっと、明日から、体調不良になってしまって、メンタルにも影響が出てくる…なんてことをしてしまったんだろうか…

腸内細菌って、そんなやわじゃないから大丈夫ですよ〜!
腸の中の細菌って、いろいろな種類がいるから!
と、いうようなやりとりとしたんですが。非常に頑張り屋さんで、これを徹底しないと、
最悪な事態になってしまう…という方向に考えてしまう癖が強いのです。
リスクを考えて対策をする「リスク管理」とは違います。
「リスク管理」と「破局的思考」の違い
「リスク管理」は、起こりうることに備え、より良い未来を築くための前向きな思考と行動です。
一方、「破局的思考」は、まだ起こってもいない、あるいは起こる可能性の低いことに心を囚われてしまう思考のことです。ありもしないことで、苦しんでしまいます。
「べき思考」(Should Statements):「〇〇すべきだ」「~でなければならない」といった、自分や他人に対する厳しいルールを作り、それに囚われる。

「べき思考」で、あなたの心を縛っていませんか?
「~すべき」「~でなければならない」。
こんな風に、自分や他人、あるいは物事に対して、「こうあるのが当たり前」「こうあるべきだ」という厳しいルールや基準を設けてしまう思考のクセを「べき思考」と呼びます。
この「べき思考」が強すぎると、そのルールから少しでも外れたときに、強い罪悪感、あるいは怒りや失望を感じやすくなります。
まるで、自分の中に「完璧な人生のルールブック」があって、それに一字一句従わないとダメだと決めつけているような状態です。
自分自身への「べき思考」
思考の例:
「良い母親なら、毎日手作りの栄養満点の食事を作るべきだ。」
「仕事ができる人なら、どんなに忙しくても、絶対にミスをしてはならないはずだ。」
「私は常に冷静で、感情的になるべきではない。」
「ダイエット中なら、一切のお菓子を食べるべきではない。」
影響:
達成困難な高い目標を自分に課し、達成できないと強い罪悪感や自己嫌悪に陥ります。常に「足りない自分」に苦しみ、心身が疲弊してしまいます。
他人への「べき思考」
思考の例:
「夫(妻)なら、私が言わなくても察して行動するべきだ。」
「子どもは、親の言うことを素直に聞くべきだ。」
「友達なら、困っている時に必ず助けてくれるはずだ。」
「店員は、常に完璧なサービスを提供するべきだ。」
影響: 他人が自分の期待通りに動かないことに強い失望や怒りを感じやすくなります。人間関係に不満を抱き、対立が生まれやすくなります。相手にもプレッシャーを与えてしまいます。
世界や物事への「べき思考」
思考の例:
「人生は、もっと公平であるべきだ。なぜ私だけこんな目に遭うんだ。」
「物事は、いつも私の計画通りに進むべきだ。」
「努力すれば、必ず報われるはずだ。」
影響: コントロールできない事態や予期せぬ出来事に対して、過剰なストレスや不満を感じます。現実を受け入れられず、不平不満ばかりが募り、幸福感が低下しやすくなります。

「べき思考」から抜け出すために
「べき思考」は、私たちを律し、目標達成を助ける側面もゼロではありません。しかし、それが過剰になると、自分自身や他人を縛り、心を苦しめてしまいます。
ゆとりがある方が、人間らしいですね^^相田みつをさんの「人間だもの」ですね〜!
まとめ
これらの心理バイアスは単独で作用するのではなく、複合的に絡み合ってオルトレキシアへとつながることが多いです。
思考や行動の縛りがひどくなってからだと、精神科や心療内科に行かなくてはならないケースもあります。「わたしそうかも…」もし、自分で気がついた時には、メンタルトレーニングをしていくことで、客観的に思考をコントロールできるようにもなります。
自分、思い当たるかも思ったら、少し立ち止まるようにしてみてくださいね。
米粉を取り入れて、家族仲良く健康食を楽しむ「米粉美人生活」体験講座は毎月、少人数制で開催しています!
健康のために米粉パンを作ってみたい。
健康的な食事を送りたいけど家族とぶつかっている。
家族が米粉のものを食べてくれずに悩んでいる。
ノンオイルの米粉パンをおいしく家族にも提供したい。
偏食の子供が菓子パンばかり食べて、米粉の手作りパンを食べてくれない。
自分がダイエットに縛られて苦しい。
シミやシワ対策ができる美味しい食生活が知りたい。
自分だけでなく、家族間の様々な悩みをお持ちの方が集まる、
米粉の取り入れ方を学び体験講座です。